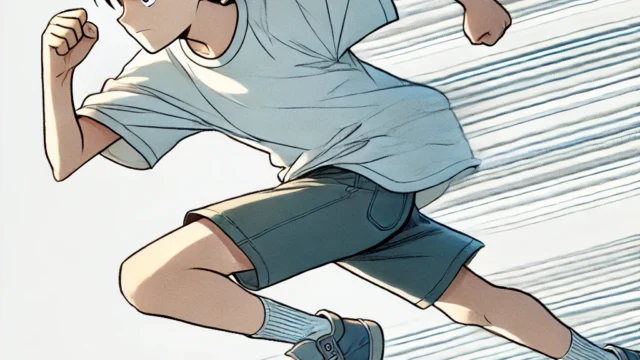「名作」と聞くと、どこか難しそうで身構えてしまうことはありませんか?
『羅生門』や『坊っちゃん』といった小説だけでなく、
『桃太郎』や『竹取物語』のような昔話、さらには日本各地に伝わる逸話の数々。
これらは、教科書や昔話集で目にしたことがあっても、
内容がなかなか頭に入ってこない、そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
それもそのはず。
これらの作品が生まれた背景には、今とは異なる時代の価値観や表現、
独特の暮らしぶりが色濃く反映されているからです。
なんとなく意味は分かっても、
登場人物の行動や物語の展開に現代とは違う違和感を覚えることもあるでしょう。
そこで、このブログでは「過去の名作を令和風に変えてみた」と題し、
名作の数々を現代に置き換えて紹介していきます。
小説、昔話、逸話──それぞれの物語を、
現代の若者や家族、日常生活を舞台にしながら、新しい視点で楽しんでみませんか?
名作が持つテーマの普遍性は、いつの時代も色あせることがありません。
令和の時代に響く新たな形で、
名作の奥深さと楽しさを一緒に再発見していきましょう!
100万回生きたねこ あらすじ(原作)
100万回死んで、100万回生きた猫は、多くの飼い主に飼われてきました。兵士、船乗り、サーカス団員など、さまざまな人々に飼われるたびに死に、そのたびに生き返る猫は、どの飼い主にも愛されましたが、猫自身は誰のことも愛していませんでした。
ある時、猫は誰にも飼われず、野良猫として自由に生きるようになります。そんな中、白く美しいメス猫と出会います。この白猫は他の猫たちとは違い、猫の過去や武勇伝にも興味を示さず、ただ静かに猫の隣にいます。
猫は初めて他者を愛する喜びを知り、白猫との生活を心から楽しむようになります。やがて二匹の間には子猫が生まれ、幸せな時間を過ごしますが、白猫が寿命を迎えて死んでしまいます。
白猫を失った猫は、深い悲しみに暮れながらも「愛する存在がいなくなった世界」に意味を見出せなくなります。そして、猫も静かに白猫の隣で息を引き取ります。それ以降、猫は生き返ることはありませんでした。
『100万回断ったぼく』 令和版:100万回生きたねこ
僕は100万回「嫌だ」と言い続けた人間だった。
子どもの頃から、自分の好きなものは絶対に譲らない性格だった。母が「一口ちょうだい」と言ってきても、僕は首を振って断った。むしろ「自分のをあげるくらいなら、母の分も奪いたい」と思うほどだった。
そんな僕が覚えている、ある日の昼食のこと。僕は肉うどんを頼んだ。母は天ぷらうどんを頼んだ。母の天ぷらうどんには、立派な海老の天ぷらが一本だけ乗っていた。
そのとき、母は何の躊躇もなく、その海老の天ぷらを僕にくれたのだ。
「いいの?」と僕が聞くと、母は笑ってこう言った。
「いいよ、智晴が食べたほうがおいしいから。」
その海老の天ぷらを口に運びながら、僕はただ「ラッキーだ」と思った。母がくれるのなら、ありがたくもらえばいい。それだけの話だった。
それは、母のいつものことだった。
唐揚げ定食では、皿に並ぶ唐揚げのほとんどを僕の方に押しやり、ステーキでは真ん中の一番分厚くてジューシーな部分を切り分けて僕の皿に載せてくれた。僕なら、絶対にあげない部分だ。それが一番おいしいから。
でも母は、何の迷いもなく、僕にくれた。まるでそれが当然のことかのように。
僕は、母が分けてくれるその「一番おいしい部分」を当たり前のように受け取り、当たり前のように食べて育った。大人になっても、自分が頼んだものを人にあげるなんて考えられなかった。彼女が「一口ちょうだい」と言ってきたとしても、断るのが僕の基本姿勢だった。
だって、それは僕が選んだもので、僕のものだから。
そんな僕も、結婚し、子どもが生まれた。最初は、子どもが僕の皿を覗き込んで「それちょうだい」と言うたびに少し戸惑った。「これは僕の分だ」と、断りたくなる気持ちを押し殺しながら、「はい」と言って渡した。
しかし、不思議なものだ。渡すたびに、子どもが笑顔で「ありがとう」と言うその顔を見ていると、何の迷いもなく次も渡してしまうようになった。
僕の大好物である唐揚げだろうが、分厚いステーキだろうが、子どもが「ちょうだい」と言えば、自然と手が伸びて皿の上に運んでしまう。そして、いつしかそれが嬉しくなっていた。
ある日、唐揚げ定食を食べている僕に、子どもが無邪気に言った。
「お父さんの唐揚げ、すごくおいしそう!」
「そうだね。おいしいよ。」
そう答えながら、僕は母がしてくれたように、一番大きな唐揚げを箸でつまみ、子どもの皿に置いた。その瞬間、母の顔がふと頭をよぎった。
母もこんなふうに、僕のために分けてくれていたのだろうか。ただ僕が喜ぶ顔を見たいという理由だけで、一番おいしい部分を僕に渡してくれていたのだろうか。
僕はその時、母の気持ちを初めて知った気がした。そして、それまでずっと「何の気なしに」もらっていたものが、どれほど大きな愛情だったかを思い知らされた。
僕は母に感謝の言葉を直接伝えたことはない。でも、母の愛情は確かに僕の中に生きている。それは、僕が子どもに「一番おいしい部分」を渡す瞬間に、自然と表れる。
100万回断ってきた僕が、今では迷いなく渡す側になった。
きっと、母もこんな気持ちだったのだろう。自分の一番好きなものを渡して、子どもの笑顔を見られる。これ以上の幸せなんて、ないのかもしれない。
「100万回断った僕」は、母から受け継いだ愛情を、今、そっと子どもに返していく。ただ、妻と子どもはいつもお菓子の取り合いをしているけれど、それはそれで微笑ましい。
100万回断った僕、とは?
「100万回断った僕」とは、自分の欲を優先し、他者に与えることをしなかった人間が、愛する存在との出会いと気づきを通じて、与える喜びを学び、成長していく物語です。
この物語は、『100万回生きた猫』と以下の点でリンクしています。
- 愛を知らない主人公の成長
主人公は子ども時代に他者を顧みず、自分中心に生きていましたが、愛する存在と出会い、愛を与える喜びに気づく点が共通しています。 - 与える愛の尊さ
『100万回生きた猫』の猫が白猫を愛したように、主人公は親となることで母の無償の愛を思い出し、愛を与えることの尊さを知ります。 - 喪失を通じて気づく愛
主人公は自分の行動を通じて、母が与え続けてくれた愛の深さに気づきます。この「喪失」と「気づき」のプロセスが両作品の共通するテーマです。
「100万回断った僕」は、『100万回生きた猫』の普遍的なテーマである愛と喪失を、日常的で身近な「親子の物語」として再解釈した作品です。
愛が巡り、次の世代へと受け継がれていく姿を描いた、もう一つの「愛の物語」と言えるでしょう。
スポンサーリンク