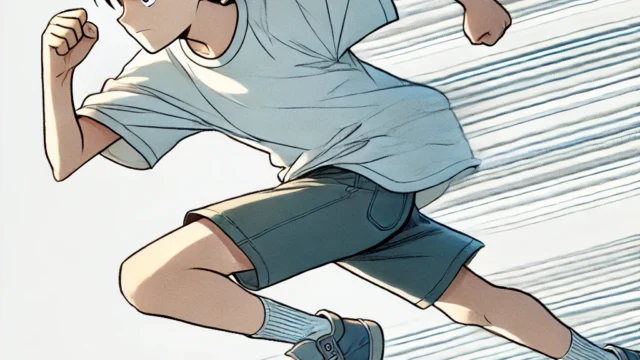「名作」と聞くと、どこか難しそうで身構えてしまうことはありませんか?
『羅生門』や『坊っちゃん』といった小説だけでなく、
『桃太郎』や『竹取物語』のような昔話、さらには日本各地に伝わる逸話の数々。
これらは、教科書や昔話集で目にしたことがあっても、
内容がなかなか頭に入ってこない、そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
それもそのはず。
これらの作品が生まれた背景には、今とは異なる時代の価値観や表現、
独特の暮らしぶりが色濃く反映されているからです。
なんとなく意味は分かっても、
登場人物の行動や物語の展開に現代とは違う違和感を覚えることもあるでしょう。
そこで、このブログでは「過去の名作を令和風に変えてみた」と題し、
名作の数々を現代に置き換えて紹介していきます。
小説、昔話、逸話──それぞれの物語を、
現代の若者や家族、日常生活を舞台にしながら、新しい視点で楽しんでみませんか?
名作が持つテーマの普遍性は、いつの時代も色あせることがありません。
令和の時代に響く新たな形で、
名作の奥深さと楽しさを一緒に再発見していきましょう!
フランケンシュタイン あらすじ(原作)
『フランケンシュタイン』は、科学者ヴィクター・フランケンシュタインが生命創造という禁忌に挑み、死体の部位を組み合わせて人造の生命体を生み出す物語です。しかし、彼の創り出した生命体は醜悪な外見をしており、その姿に恐怖したフランケンシュタインは彼を放棄します。
見捨てられた怪物は、自分の存在意義を求めながらも人間社会に拒絶され、孤独と怒りの中で復讐を決意します。フランケンシュタインの愛する人々を次々に襲い、彼との関係は絶望的な対立へと発展。物語の終盤では、怪物が自らの悲劇的な運命を嘆きながら北極で消えていきます。
この作品は、科学技術の進歩とその危険性、倫理の限界を問いかける一方、孤独や人間性の本質を深く探求しています。
令和版:フランケンシュタイン
【シン・フランケンシュタイン】
プロローグ
「咲ちゃんは本当に可愛いね。」
祖母は幼い私を膝に抱えながら、毎日のようにそう言ってくれた。
けれど、その言葉を信じるのは難しかった。鏡に映る顔は地味で、何の特徴もない。「可愛い」どころか、どこにでもいる「普通」の顔。両親も私をほめることはなく、学校では「地味子」とからかわれることが日常だった。
「おばあちゃんだけだよ、そんなこと言うの。」
そう呟いた私に祖母は微笑み、そっと頬に手を当てた。「だって、本当のことだもの。」
その言葉だけが、幼い頃の私を支える唯一の光だった。
第1章: 美しさへの渇望
26歳になった私は、未だに外見への劣等感を抱えていた。SNSには完璧な顔をした「美しい人々」が溢れ、私はその中に属さない惨めさに押しつぶされそうだった。
「私も変われるだろうか……。」
ある日、SNSの広告が目に入った。「あなたの人生を変える整形術」「奇跡の整形外科医」というキャッチコピーと劇的なビフォーアフターの写真が目を引いた。
執刀医・城山一樹。写真には笑顔の彼と、「夢を叶えてくれた」患者たちの感謝の言葉が並んでいた。
「今まで自分に自信がなくて恋愛も諦めていました。でもこの手術で生まれ変われました!」
「夢のような変化。これでやっと本当の自分に出会えました。」
その文章を読んだとき、私は胸の奥に灯がともるのを感じた。「これだ、これが私の人生を変える鍵だ」と確信した。
「自分だけが見逃してきた扉が、いま目の前に開かれている。」
その感覚は、これまで私が抱えてきたコンプレックスや孤独感を一瞬でかき消してくれるほど強烈だった。私がずっと探していた「本当の私」になれる。
──そんな錯覚を抱かせる巧妙な罠だったと気づいたときには、もう手遅れだった。
第2章:手術の失敗と怪物化
初めて会った城山一樹は、いかにも自信に満ち溢れた人物だった。
「お任せください。私の手にかかれば、あなたも生まれ変われますよ。」
彼の言葉には魔力があり、私は完全に信じきってしまった。だが、その笑顔の裏には冷徹な思考が隠されていた。
手術後、私の顔は醜く腫れ上がり、皮膚は壊死したように黒ずんでいた。必死で城山に連絡したが、彼は軽く笑って言った。
「大丈夫ですよ。時間が経てば綺麗になりますから。」
その声は自信に満ちていたが、どこか投げやりな響きもあった。その瞬間、私の胸にかすかな疑念が浮かんだ。
そして、私の疑念は確信へと変わった。痛みと恐怖の中で過ごす私をよそに、クリニックは突然閉鎖されたのだ。そしてニュースで彼が無免許医師であり、違法な整形手術を繰り返していたことを知った。
その事実を知って愕然としている私に、追い打ちをかけるような日々が待ち受けていた。
変わり果てた顔を見た職場の同僚たちは、私を避けるようになった。
「咲さん、ちょっと……怖いよね。」
そんな言葉が聞こえてきたとき、私は全身が凍りついた。
昼休みに誘ってくれていたグループも、今では私を無視する。上司からも、「顧客対応は控えるように」と言われ、内勤への異動を命じられた。
家族も私を受け入れてはくれなかった。
「咲、どうしてこんなことになったの?……お母さん、近所の人に何て言えばいいの?」
母のその言葉は、私を完全に孤独に追い込んだ。
スーパーで子どもに「おばけみたいだ」と指を差され、隠し撮りされた写真がSNSで拡散される。「グロい」「どうして外に出るの?」といったコメントが並び、私は二度と外に出られなくなった。
鏡に映る自分の顔を見るたびに、胸の奥から怒りが湧き上がる。
「私は怪物になった……あの男のせいで。」
第4章:城山一樹の背景
城山一樹は、かつて医学部に在籍していたが、学生時代から周囲に劣等感を抱えていた。上位層の同級生たちが次々と難関資格を取得し、教授から称賛される中、彼は学問よりも実践に興味を持つ「変わり者」と見なされ、孤立していた。
「資格なんて形式だ。俺は誰よりも手術の技術がある。」
彼は学生時代から人形や動物で独学の手術練習を続け、その技術を同級生に誇示していた。しかし卒業試験に失敗し、資格を得ることができなかったことから、正式な医師への道を絶たれる。
それでも彼は諦めなかった。資格がなくとも人々を救えるはずだ──そう信じていた。しかし、最初の数件の「成功例」が彼の倫理観を歪ませていった。患者が感謝の涙を流すたびに、彼は自らを「天才」と確信した。
「資格が何だ。患者が望む結果を出せるかどうか、それだけが問題だ。」
だが次第に、結果よりも「成功した自分を見せつけたい」という欲望が勝り始めた。SNSでの自己アピール、ビフォーアフターの写真、患者の感謝の声。それらは全て彼の野心を掻き立て、ついには安全基準や手術適性を無視するようになっていった。
第5章: 復讐への道
孤独と憎しみに突き動かされ、私は城山への復讐を決意した。彼が都内の高級マンションに隠れていることを知ると、ネットで彼の行動パターンを調べ上げた。
ある夜、私はナイフをポケットに忍ばせ、彼の部屋に足を踏み入れた。ドアが閉まる音に気づき、彼は振り返った。最初は私が誰なのか分からなかったのか、怪訝そうな顔をしていたが、次の瞬間、顔を歪めて笑った。
「おや、また失敗患者か。そんな顔でここまで来るとは大した根性だな。」
言葉を切り、私を見下ろすように吐き捨てた。
「それで、その顔になったのは君自身の選択だろう?責任転嫁もいい加減にしてくれ。」
その瞬間、私の中で何かが切れた。胸の奥で膨れ上がる怒りが、一気に爆発した。
「私の人生を壊したくせに……!」
叫びながらナイフを握りしめた手に力が入る。彼に向かって一歩、また一歩と近づく。
しかし、振り上げたナイフが空中で止まる。心の奥底から、もう一人の自分がささやいてくる。
「本当にこれでいいの?これが私の望んでいたことなの?」
ナイフを握る手が震える。目の前の男はただの無力な人間だ。確かに私を壊した張本人だが、この行為で私自身も壊れてしまうのではないか。
「今なら引き返せる……」
だがそのとき、城山が低い笑い声を漏らした。
「そんな顔をして何をためらっている?お前みたいな醜い女に何ができる?」
その言葉が私の中に火をつけた。全身を駆け巡る怒りが、理性を打ち砕いた。
「もう、許さない……!」
私はナイフを振り下ろした。その刃が彼の体に触れる感触と共に、体が震えた。命乞いの声が耳に届くが、私はその手を止めることができなかった。
第6章:復讐後の空虚感
すべてが終わった。彼が動かなくなった部屋の中には、私の荒い息遣いと時計の音だけが響いていた。
ナイフを握りしめた手を見下ろすと、血が滴り落ちている。私が「怪物」と化した瞬間がそこにあった。
「これで終わったんだ……」
そう自分に言い聞かせたが、胸の中に湧き上がるのは安堵ではなかった。達成感はほんの一瞬で消え去り、代わりに押し寄せてきたのは重い罪悪感だった。
「私は、こんなことをするために生きているわけじゃなかった……」
床に崩れ落ちながら、手に付いた血を何度もこすり落とそうとした。だが、いくらこすっても血は落ちない。その赤い痕跡は、私が取り返しのつかないことをした証拠だった。
部屋の中で虚ろな目をして座り込む私に、城山が言っていた言葉が何度も蘇る。
「この顔になったのは君のせいだ。」
あの言葉を否定するためにここまで来たはずなのに、今の私もまた、彼の言う「醜い存在」になり果ててしまったのではないか──そんな思いが頭を締め付ける。
第7章: 事件の波紋
ニュースでは、私の行動が「無免許整形が生んだ悲劇」として大きく取り上げられた。SNSでは私への同情と批判が渦巻き、他の被害者たちが次々と声を上げるきっかけとなった。
「私たちの代わりに、あの人が行動してくれた。」
「私も被害を受けた一人です。彼女の勇気を無駄にしてはいけない。」
事件は社会に波紋を広げ、美容整形業界の問題が浮き彫りとなった。広告の規制や医師免許の確認を強化する法案が提出され、無免許医師への罰則も厳しくなった。
だが、私は何も感じなかった。すべてを失い、怪物と呼ばれた自分が、いまさら何を取り戻せるというのだろうか。
第8章: 刑務所での再会
刑務所での孤独な日々。私は、こんな醜い姿を祖母には見せられないと面会を拒否し続けていた。だがある日、祖母がどうしても会いたいと訪れてきた。
面会室で目の前に立つ祖母は、変わり果てた私を見ても何一つ変わらず微笑んでいた。その穏やかな表情が、私の胸に痛みを与えた。
「咲ちゃん、大変だったね。」
その優しい声が耳に届くと、堰を切ったように涙が溢れた。
私はうつむき、泣きながら言った。
「おばあちゃん……もう私は怪物だよ。こんな顔になって、誰からも怖がられて……。可愛いなんて、言わないで。」
祖母は静かに首を振り、変わらず優しい声でこう言った。
「誰がそんなことを決めたの?咲ちゃんは世界一可愛いよ。今も、昔も、これからも。」
その言葉に、私は声を上げて泣いた。
第9章:怪物にはなれない
祖母が帰った後、独房の中でひとりきりになった私は、祖母の言葉を反芻していた。
「誰が決めたの?」
私は自分を「怪物」だと決めつけてきた。醜く変わり果てた顔を見た人々が私を拒絶し、恐れ、切り捨てたからだ。でも、それは本当に私が「怪物」だったからだろうか?
目を閉じると、城山の冷たい笑みが浮かぶ。私を騙し、壊したあの男。彼こそが「怪物」ではなかったのか?自分の利益のために他人を利用し、その結果に何の責任も負おうとしない彼。
外見だけで人を評価し、少しでも「普通」と違えば排除しようとする残酷な社会。
「怪物は、私じゃない……。」
城山を追い詰めたあの夜、私は心のどこかで後悔していた。ナイフを振り下ろす瞬間、自分の中で微かに響いた「やめろ」という声を振り切ることで、私は彼を傷つけた。もし、あの声を完全に無視できていたら、あるいは後悔などしない完全な「怪物」になれていたのだろうか?
私が感じているこの痛みや罪悪感、それがある限り、私は「怪物」にすらなれない。ただ、怪物のふりをした未熟で弱い人間なのだ。
エピローグ
看守から一通の手紙を手渡された。手紙の封を切ると、ぎこちない文字で書かれたメッセージが目に飛び込んできた。
「あなたのおかげで、私も声を上げることができました。もう一人で悩まなくていいと感じられるようになりました。本当にありがとう。」
手紙には他の被害者たちの感謝の言葉が連なっていた。
「私たちも、あなたのように強く生きたい。」
「あなたが行動してくれたから、救われた人がいるんです。」
手紙を読み進めるうちに、胸の奥が熱くなった。あの復讐の夜、私は自分を怪物にしてしまったと思っていた。だが、その行動が誰かの心を救うきっかけになったのだと知ったとき、私は初めて自分の存在が無駄ではなかったと思えた。
独房の小さな窓から見える星を眺めながら、私はそっと呟いた。
「たとえ怪物と呼ばれても、私の行動が誰かの役に立ったなら……それでいい。」
祖母が教えてくれた「誰が決めたの?」という問いが、私の心の中に希望を灯してくれた。私はまだここにいる。これからも、生きていける。
令和版フランケンシュタインとは
【シン・フランケンシュタイン】は、美容整形の失敗によって「怪物」とされる女性が主人公の物語です。外見に基づく偏見やSNS社会の残酷さ、復讐と自己受容の葛藤を描き、現代社会における「怪物」とは何かを問いかけます。
原作のテーマである「科学と倫理の衝突」を現代の美容整形と結びつけ、人間性や社会の在り方を深く探求した新解釈です。
スポンサーリンク